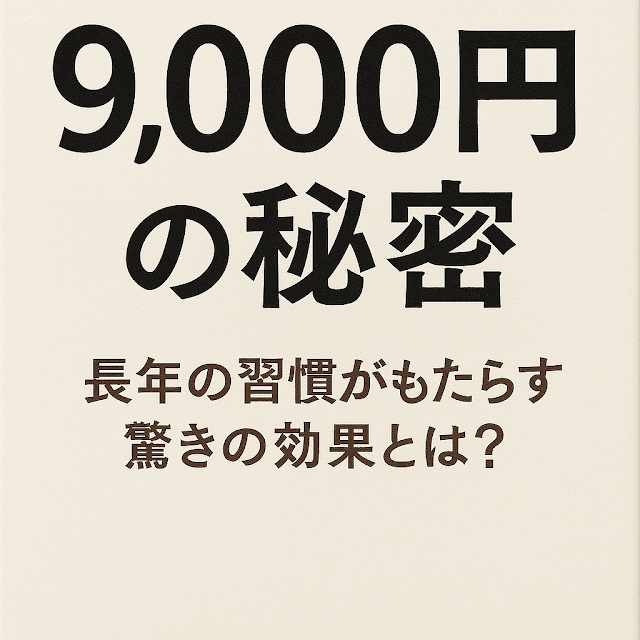原題:『後の祭』
(1)祭りの翌日,供え物を下げて飲食すること。後宴。
(2)〔祭りのすんだあとの山車(ダシ)の意から〕時機を逸してかいのないこと。ておくれ。
(大辞林より)
京都三大祭りのひとつ、祇園祭が7月1日から始まりました。
祇園祭というと、露店が並んで大勢の人々でにぎわう14日~16日の「宵山」や、四条河原町などでは敷いた青竹の上を巨大な鉾がきしむ音をたてて90度向きを変える「辻回し」も見事な、17日の「山鉾巡行」が目立ってしまっているため、これらが祇園祭だと勘違いされていることがありますが、違います。
祇園祭は7月1日の各山鉾町による神事始めである「吉符入り」に始まり、31日の八坂神社境内での「疫神社夏越祭(えきじんじゃなごしさい)」までの1ヶ月に渡って各種神事や行事が行われる、約1150年の伝統を有する八坂神社の祭事です。
昭和40年代から山鉾巡行を中心として観光祭のようになってきました。
元々は山鉾巡行は神霊の来訪を歓迎するいわば”パレード”に過ぎませんでしたが、室町初期にはすでに町衆の関心は山鉾に移っていたと言われています。
しかし、本当は八坂神社および祇園周辺で行われる祭事が八坂神社にとってホントに重要な行事、祇園祭本来の主要行事であり、八坂神社主体で行われる祭事は古式に乗っ取って伝統を護ってます。
ちなみに、昔と今とでは山鉾巡行のルートは違いますが、昔も今も山鉾は現在の「祇園」と呼ばれる場所を通ることはありません。
古くは、祇園御霊会(ごりょうえ)と呼ばれ、869年(貞観11年)に京の都をはじめ日本各地に疫病が流行したとき、「これは祇園牛頭天王の祟りである」として、平安京の広大な庭園であった神泉苑に、当時の国の数である66ヶ国にちなんで66本の鉾を立て、祇園の神を祭り、さらに神輿をも送って災厄の除去を祈ったことに始まります。
祇園祭の行事は主に、
1.山鉾巡行、花傘巡行に関するもの
2.神輿渡御に関するもの
3.奉納行事
4.神社における祭り全体の神事
に大きく分けることができます。
この中で17日の山鉾巡行は1番にあたります。
17日の巡行が終わったその夕方ごろ、八坂神社から中御座(素戔嗚尊:すさのおのみこと)、東御座(櫛稲田姫命:くしなだひめのみこと)、西御座(八柱御子神:やはしらのみこがみ)の3基の神輿が鷲舞行列を先頭に発輿し、氏子区域内を3基とも別ルートを通りながら四条寺町の御旅所まで渡御します。
これが2番のうちの一つで「神幸祭」と言い、先に書いたようにこの神輿渡御こそが祇園祭の中心なのです。
わたしは京都に住んでいた4年間、毎年バイトで神輿渡御に参加していました。
神輿が普通に移動するときはいいのですが、途中の「本ガキ」のときはしっかりと神輿を振り回して先端部・最後部にある「カン」を鳴らさないといけません。
そして御旅所に到着したときにここでまた最後の力を振り絞って「カン鳴らし」と「さし上げ」をし、御旅所への収納を経て神幸祭は終了です。
これら以外に1日から日を追うごとに「くじ取り式」、「稚児舞披露」、「お迎え提灯」、「神輿洗」、「長刀鉾稚児社参」、「久世駒形稚児社参」、「鷺舞」、「田楽」、「石見神楽」、「無言参り」など数多くの行事があります。
たまに深夜のバイト帰りに、無言参りをしている芸妓さん、舞妓さんを見かけましたが、なかなか良いもんですね。
さて、ハイライトの山鉾巡行が終わってしまうと祇園祭が終わったかのように感じます。
しかし、祇園祭は31日まで続きます。
ではこの後に何があるかというと・・・・・・『後の祭』です。
祇園祭の山鉾巡行は「前祭(さきまつり)」(17日)と「後祭(あとまつり)」(24日)の二度あります。
1966年に後祭が前祭に合同され、後祭の巡行は前祭の巡行の直後に続く形になり、後祭の巡行日であった24日には花笠巡行が創設されました。
ですが、2014年に後祭が復活し、24日に山鉾巡行と花笠巡行が行われます。
花傘巡行は後祭が衰退するのを防ぐ為に開始された祇園祭の古い形態を再現したもので、花傘は山鉾の古い形態を再現しています。
巡行には四つの花街の綺麗処や稚児をはじめ、六斎、鷺舞、祇園囃子の曳山や、傘鉾10基余など総勢1,000人の行列が京の町を練り歩きます。花車には芸妓さん、舞妓さんらが乗っています。
また、夕方には「還幸祭」として、神幸祭で四条御旅所に収納された3基の神輿が氏子区域内をまたも3基とも別ルートで練り歩き、三条御供社にて神事を執り行い、その後、八坂神社に還幸し神霊を八坂神社に還します。
そして「神輿洗」や「神事済奉告祭」があり、最後の31日に八坂神社境内にある蘇民将来を祭る疫神社にて、祇園祭関係者が鳥居に掛けられた直径2.5mの茅の輪(ちのわ)をくぐって厄気を祓って無病息災を祈願し、また「蘇民将来之子孫也」の護符を授かります。もちろん、一般参詣者もお参り出来ます。これが「疫神社夏越祓」で、これで1ヶ月におよぶ祭事が終わります。
ことわざで『後の祭』という言葉がありますが、これは後祭は前祭に比べていまいち盛り上がりに欠けることから、遠くから来た人がいいところを見逃して、「ああ、もう後祭だ(遅かったか)」と言ったことからきている説があります。
ですが、昔はそうであったかもしれませんが、復活した後祭はどうでしょうか?
【2025年7月加筆】
[Updated Jul 2025]
『後の祭』の記事を読んだ人に次に提供すべき情報として、2025年7月時点の最新情報を加味してまとめました。
祇園祭の概要と歴史
祇園祭は、京都の八坂神社で行われる日本三大祭りの一つで、7月1日から31日までの1ヶ月間にわたって開催されます。祇園祭は、869年(貞観11年)に疫病退散を祈願して始まったとされ、約1150年の歴史を持つ伝統的な祭りです。祭りの中心行事は、山鉾巡行と神輿渡御であり、これらは前祭(さきまつり)と後祭(あとまつり)に分かれています。
前祭と後祭の違い
祇園祭は、7月17日に行われる前祭と、7月24日に行われる後祭に分かれています。前祭では、23基の山鉾が巡行し、後祭では10基の山鉾が巡行します。前祭と後祭の違いは以下の通りです:
- 前祭(さきまつり):7月17日に行われ、23基の山鉾が巡行します。宵山(よいやま)と呼ばれる前夜祭が14日から16日にかけて行われ、多くの露店や屋台が並び、賑わいを見せます。
- 後祭(あとまつり):7月24日に行われ、10基の山鉾が巡行します。後祭の宵山は21日から23日にかけて行われ、前祭に比べて落ち着いた雰囲気があります。
2025年の祇園祭の見どころ
2025年の祇園祭では、以下の見どころがあります:
- 鉾曳き初め(ほこひきぞめ):7月20日と21日に行われる鉾曳き初めは、山鉾が初めて動く様子を見学できる貴重な機会です。大船鉾や鷹山など、最近復活した山鉾の曳き初めは特に注目されています。
- 山鉾巡行:前祭の山鉾巡行は7月17日、後祭の山鉾巡行は7月24日に行われます。巡行ルートは、烏丸御池から出発し、御池通、河原町通、四条通を巡ります。辻回しと呼ばれる山鉾が90度回転する様子は圧巻です。
- 神輿渡御:神輿渡御は、7月17日の神幸祭と7月24日の還幸祭の2回行われます。神輿が氏子区域を巡行し、八坂神社に戻る様子は見逃せません。
祇園祭の最新情報
2025年の祇園祭に関する最新情報は以下の通りです:
- 日程と時間:前祭の山鉾巡行は7月17日午前9時から、後祭の山鉾巡行は7月24日午前9時30分から開始されます。鉾曳き初めは7月20日と21日に行われます。
- アクセス:最寄り駅は京都市営地下鉄四条駅で、京都駅から約4分です。四条駅から各山鉾町までは徒歩10分以内で到着します。
- 駐車場:無料駐車場はありませんが、有料駐車場が複数あります。例えば、山田パーキングやタイムズ四条西洞院第2などが利用可能です。
祇園祭の楽しみ方
祇園祭を楽しむためのポイントをいくつか紹介します:
- 早めの到着:特に鉾曳き初めや山鉾巡行を見学する場合は、早めに到着して場所を確保することをおすすめします。
- 涼しい服装:7月の京都は非常に暑いため、涼しい服装と帽子、日焼け止めを準備しましょう。
- 水分補給:熱中症対策として、こまめに水分補給を行いましょう。
- カメラの準備:山鉾や神輿の美しい装飾を撮影するために、カメラを忘れずに持参しましょう。
祇園祭の歴史と文化
祇園祭は、京都の町衆文化を象徴する祭りであり、地域の人々が一体となって行事を支えています。山鉾の装飾や祇園囃子(ぎおんばやし)など、伝統的な技術や芸能が受け継がれており、訪れる人々に感動を与えます。
まとめ
祇園祭は、京都の夏を彩る一大イベントであり、歴史と伝統が息づく祭りです。2025年の祇園祭も、多くの見どころやイベントが予定されており、訪れる人々にとって忘れられない体験となることでしょう。ぜひ、早めの計画と準備をして、祇園祭を存分に楽しんでください。

オリジナル投稿:2024年7月2日