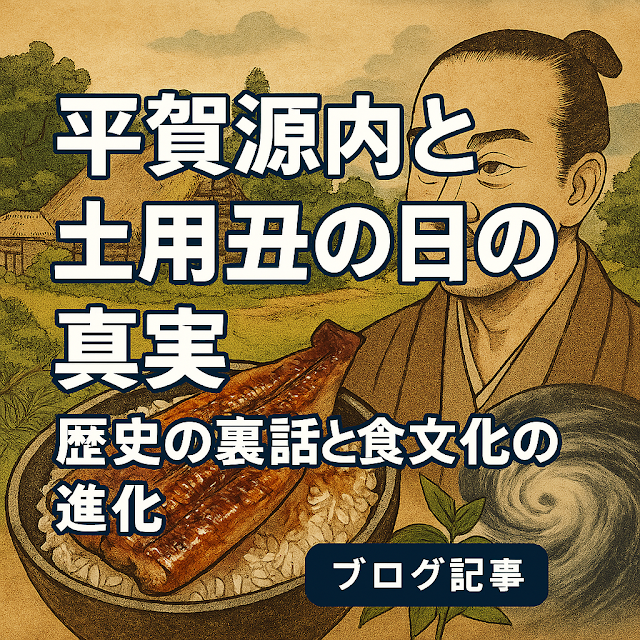原題: にちようのどようをにちように 平賀源内の策略
毎日暑いですね。
こうも暑いと夏バテしてしまいそうですね。
ということで、今日2023年7月30日は『土用丑の日』。
鰻でも食べますか?
『土用丑の日』と言えば、
商売がうまくいかない鰻屋が、夏に売れない鰻を何とか売るため平賀源内に相談したところ、源内は「本日丑の日」と書いて店先に貼ることを勧めました。すると、その鰻屋は大変繁盛し、ほかの鰻屋もそれを真似るようになり、土用の丑の日に鰻を食べる風習が定着した
という話が有名です。
でも、これは嘘、というか、そうだと記された史実や書き物などの証拠・根拠がないんですよね。
という話も有名ですね。
元々は、丑の日に『う』の字が付くものを食べると夏負けしない、という風習があったそうで、瓜や梅干し、うどん、うさぎ、ウマ、ウシなどは食べられていたそうです。
なお、日本各地の貝塚から鰻の骨が出土するそうで、日本人が鰻を食すことは縄文時代から続いているようです。
また、鰻に関しては日本最古の歌集『万葉集』にも記載されており、
石麻呂(いはまろ)に われ物(もの)申(まを)す 夏痩(やせ)に
良(よ)しといふ物そ 鰻(むなぎ)取り食(め)せ
訳:石麻呂に私は申し上げたい。夏痩せによいというものですよ。鰻をとって召し上がりなさい。
痩(や)す痩(や)すも 生(い)けらばあらむを はたやはた
鰻(むなぎ)を取ると 川に流るな
訳:いくら痩せていても、生きていられれば良いではありませんか。間違っても鰻を捕るために川に入って流されたりしないようにしてください。
どちらも吉田老(よしだのおゆ)と言う教養がある立派な人物に、大伴家持(おおとものやかもち)が詠んだ歌です。
奈良時代には鰻は滋養強壮に良い、という認識があったようで、現代まで残る文献で鰻の効用を初めて書き記したのがこの大伴家持の万葉集の歌になります。
そもそも『土用』とは、立春・立夏・立秋・立冬の前の各18日間のことで、その期間内の丑の日が『土用丑の日』となります。
長野県岡谷市の鰻店などで結成された「うなぎのまち岡谷の会」が”夏の土用丑の日のように冬の土用にも鰻を食べよう”として立春前にあたる1月最終の丑の日を『寒の土用丑の日』を1998年(平成10年)に制定、一般社団法人 日本記念日協会に登録されているほか、商標登録(登録4525842)もされています。
さて、最初の平賀源内の話に戻って、もし仮に源内の話が本当であって、その当時に商標登録制度が存在していて、例えば『大暑の土用丑の日』などと商標登録していたならば、とんでもないことになっていたかもしれませんね。
【2025年7月加筆】
[Updated Jul 2025]
🌟 平賀源内の伝説を超えて:土用丑の日の広がり 🌿
「にちようのどようをにちように」の記事は、平賀源内の策略が広げた風習「土用丑の日」にスポットライトを当てたユニークな視点を提供しています。本提案では、その歴史的背景をさらに掘り下げつつ、現代の視点で再解釈し、読者が深く共鳴できるテーマを探求します。
1. 平賀源内の世界観:その策略が生んだ新たな文化
平賀源内といえば「土用丑の日」のうなぎにまつわる説話が有名です[^6^][^7^]。そのインパクトはただの商業的成功にとどまらず、日本人の食文化や社会習慣を形作ったと言えるでしょう。以下では、源内の影響力をさらに深く掘り下げます。
- 歴史を彩る平賀源内: 「う」のつく食べ物を普及させたことで、現代日本の健康意識にも通じています。
- 影響の進化: 平賀のアイデアが、現在のスローライフやエコフードの潮流にも影響を与えた可能性。
2. 土用丑の日の現代的意味:健康とサステナビリティ
2025年の土用丑の日(7月19日と31日)を例にとり、今日の私たちがうなぎや「う」のつく食材の重要性をどのように捉えているかを解説します[^6^][^9^][^10^]。
- 健康の視点: うなぎに含まれるビタミンA・B群の効用を現代医学で解説。
- 持続可能な選択肢: うなぎの資源保護と代替食材の提案(ウリ科の野菜、しじみ、梅干し)。
3. 地域独自の土用丑の日イベント:過去から未来へ
全国各地で行われている土用丑の日のイベントを紹介します[^8^][^9^]。
- 長野県岡谷市の「寒の土用丑の日」: 冬季限定のイベントが進化し、持続可能性と結びついています。
- 地域ごとのユニークな風習: 各地の神社で行われる「きゅうり加持」や、「丑湯」のリラックス効果。
4. 「う」のつく食材をめぐる旅とガイド
平賀源内のアイデアを生かして、全国の特色ある食材を巡る旅を提案します[^7^][^8^]。
- おすすめスポット:
- 梅干しの本場、和歌山: クエン酸たっぷりの梅干しが疲労回復を促進。
- スイカ農園巡り: 群馬県などでフレッシュなスイカを味わう。
5. 古代から未来へ続く「土用」の知恵
縄文時代から続く鰻の食文化の背景に触れながら、土用の丑の日が日本の文化にどのような影響を与えてきたかを考察します[^9^][^10^]。
- 文献に見る鰻の効用: 万葉集の記述から読み取る鰻の歴史的価値。
- 未来の土用丑の日: テクノロジーを活用した新しい健康食品の登場。
まとめ
この記事を読んだ方々には、平賀源内が創り出した文化の広がりや土用丑の日の新しい楽しみ方を紹介することで、知識を深めるとともに現代に生きる意義を再認識していただければ幸いです!さらに具体的なテーマや質問があれば、ぜひお知らせくださいね✨🍃